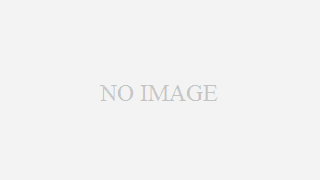 Uncategorized
Uncategorized 原神6.0アップデートがついに到来!ナドクライや新キャラ追加で冒険がさらに広がる
原神の最新バージョン6.0「Luna1」が、2025年9月10日(水)のメンテナンス後に実装され、これまで以上に多くの新要素と改善が盛り込まれています。新しい国「ナドクライ」の登場や、新キャラクター・復刻キャラクターの追加、イベントや機能...
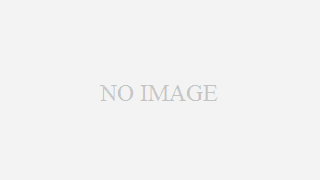 Uncategorized
Uncategorized 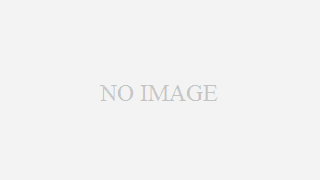 Uncategorized
Uncategorized 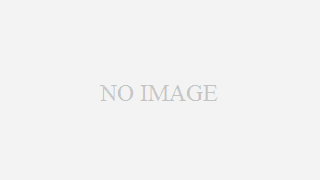 Uncategorized
Uncategorized 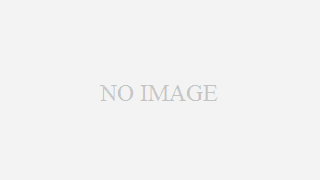 Uncategorized
Uncategorized 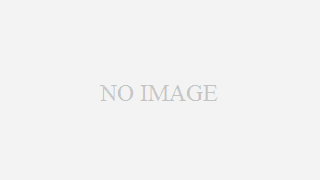 Uncategorized
Uncategorized 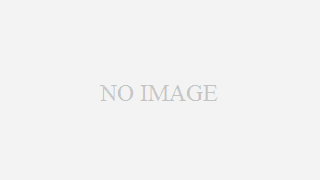 Uncategorized
Uncategorized 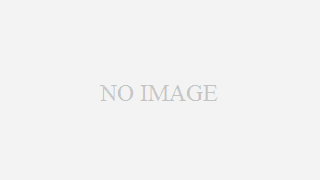 Uncategorized
Uncategorized 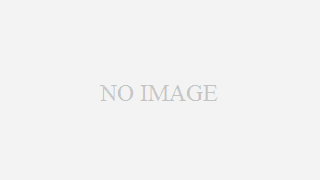 Uncategorized
Uncategorized 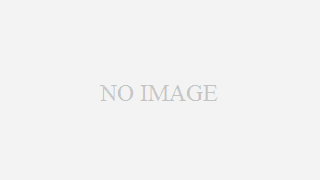 Uncategorized
Uncategorized 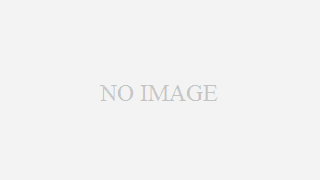 Uncategorized
Uncategorized