ガソリン暫定税の廃止が検討される中、その代替財源として浮上している「走行距離課税」。一見公平に見えるこの制度には、実は多くの矛盾や問題点が潜んでいます。「たくさん走るクルマほど多く税金を払え」という発想そのものが抱える根本的な欠陥を、ズバリ指摘していきましょう。
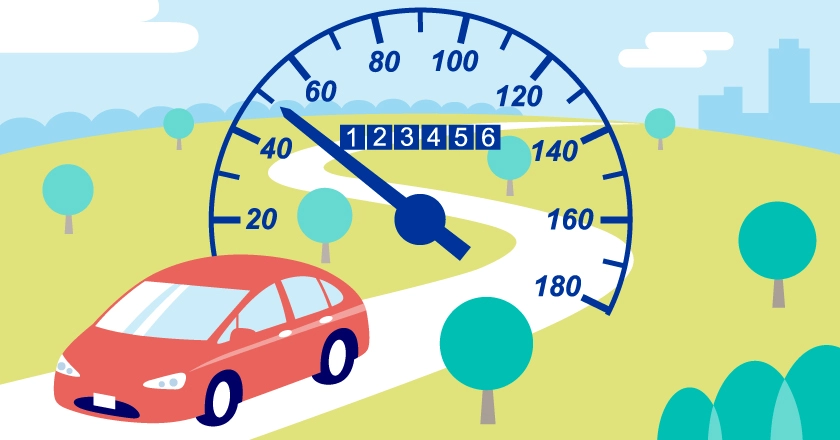
矛盾点1:地方住民への不公平さ
都会と地方の移動格差を無視
走行距離課税が最も不公平な点は、都市部と地方の移動環境の違いを完全に無視していることです。地方では公共交通機関が乏しく、車がなければ生活できません。スーパーへ買い物に行くにも、病院へ通院するにも、都会よりはるかに長い距離を走らなければならないのです。
事実上の「地方居住罰金」
この制度は、地方に住むというだけで、都会の住民より多くの税金を支払うことを強制します。これは移動の自由や居住の自由を侵害する「地方居住罰金」に等しいと言えるでしょう。
矛盾点2:プライバシー侵害の危険性
移動の監視社会への道
走行距離を課税基準にするためには、政府が国民の移動距離を把握する必要があります。GPSによる位置情報の収集や、走行データの記録は、監視社会への第一歩です。
「どこを」「いつ」「どのように」走ったかまで把握
単なる距離だけでなく、走行経路や時間帯まで把握できる技術が使われる可能性があります。これは明らかなプライバシー侵害であり、自由な移動という基本的人権を脅かすものです。
矛盾点3:環境対策としての矛盾
EV推進との矛盾
政府は電気自動車(EV)の普及を推進しながら、一方で走行距離に課税しようとしています。これでは「環境に優しい車に乗っても、使えば使うほど罰金」という矛盾したメッセージになってしまいます。
本当の環境対策とは程遠い
本当の環境対策なら、走行距離ではなく、排気量や燃費性能、使用燃料の種類で課税すべきです。走行距離課税は、環境対策というより単なる財源確保の方便に過ぎません。
矛盾点4:実現性とコストの問題
莫大な導入コスト
新しい課税システムを導入するには、車両への計測機器搭載や、データ管理システムの構築に莫大な費用がかかります。これらのコストは結局、国民の負担になるでしょう。
複雑な税制のさらなる複雑化
現在でも自動車税、重量税、消費税など複数の税金が存在します。走行距離課税を追加すれば、税制はさらに複雑化し、国民の理解を得られないでしょう。
まとめ文
走行距離課税は矛盾だらけの欠陥制度であり、導入すべきではありません。地方住民への不公平、プライバシー侵害、環境対策としての矛盾、実現性の欠如など、根本的な問題が多すぎるからです。例えば、都会に住む週末ドライバーと、地方で日常的に長距離移動せざるを得ない人では、必要な移動距離が根本的に異なります。同じ走行距離でも、生活必需度が全く違うのです。したがって、走行距離課税ではなく、既存税制の抜本的な見直しや、真に公平で実現可能な財源確保策を検討すべきです。この欠陥制度の導入には強く反対するべきでしょう。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-how-to-check-mileage
コメントを残す